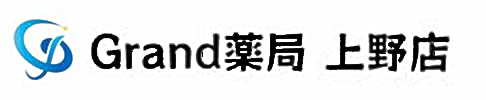【漢方】水の異常について
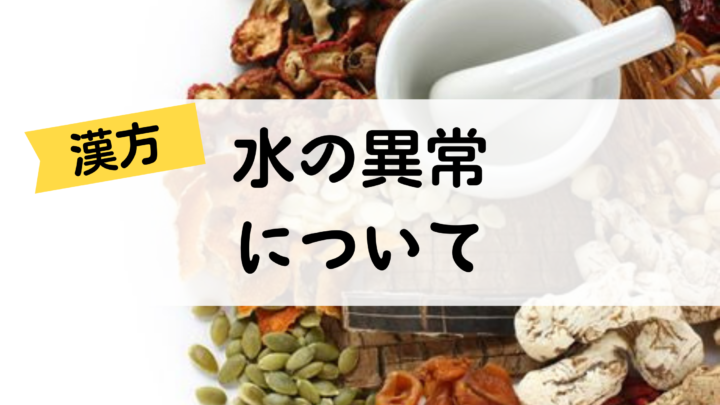
今回は、「気・血・水」の水について解説いたします。
水は体内を潤す作用があり、津液と呼ばれます。
血液以外の水分(鼻水や唾液、リンパ液など)を指します。
この水の異常が様々な体調不良を引き起こすと言われています。
水の異常にはどのような症状、対策があるのでしょうか?
詳しく解説していきます。
気・血・水については、別記事にてそれぞれ解説しておりますので、そちらをご参照ください。
→【気・血・水について】
水の異常の種類
水の異常には、「水毒(水滞)」と呼ばれる異常があります。
水毒(水滞)について
水滞は時の如く、体の”水”の巡りが悪くなった状態です。
本来であれば水分は余分に溜まることはありません。
何らかの原因によって溜まってしまった状態を指します。
(※水とは、体液や汗、唾液、胃液、腸液、尿などの液体も含みます。)
水滞になると、余分な水や老廃物が溜まりやすくなります。
また、特に胃腸などは”湿邪”におかされやすくなり、胃もたれや食欲不振などの症状が顕著に現れます。

水滞の原因
水滞の原因としてましては、以下が挙げれます。
①水分の摂り過ぎ
②お酒の飲み過ぎ
③内臓機能の低下
④自律神経の乱れ
⑤体の冷えすぎ
⑥筋肉不足
などなど…
水滞の症状
頭痛、頭重感、むくみ、めまい、頻尿、胃腸障害、下痢、手足の冷え、雨の日の体調不良、関節痛など
また、水滞の場合、舌に歯の形がくっきりしていることが多いです。
お腹を軽く叩いた時にチャポチャポした音が鳴る時は水滞状態です。
水滞に処方される漢方薬
水滞によく使われる漢方薬をご紹介いたします。
◎五苓散
→頭痛、下痢
◎猪苓湯
→排尿痛、下痢
◎真武湯
→冷え、倦怠感、易疲労感、めまい、むくみ、下痢
◎越婢加朮湯
→関節痛、水疱湿疹
◎防已黄耆湯
→関節痛(膝)
◎六君子湯
→胃腸障害、食欲不振
◎人参湯
→冷えによる胃腸障害
◎呉茱萸湯
→吐き気、頭痛
水滞の対策
適度の体を動かしましょう。
筋肉は体内の水分などを循環させる役割があるため、筋肉量が少ないと水滞になりやすいと言われております。
夏場はエアコンにより胃腸が冷えやすいので、冷たい食べ物の食べ過ぎ・飲み過ぎには注意が必要です。
まとめ
今回は、「気・血・水」の水の異常を解説いたしました。
雨の日や梅雨の時期、台風などの天候異常の際に体調を崩される方が多く見受けられます。
よくある症状とましては、頭痛です。
これは水滞である可能性があり、漢方薬を使用すると改善します。
今後も漢方の豆知識を発信していきます。
お楽しみに!
LINEの登録で『全商品20%OFF』に!
各種お問い合わせいただけます♪
◎お薬の在庫確認
◎お薬のお取り置き
◎その他ご質問
LINEであれば場所・時間を問わず
簡単にお問い合わせができます(^^ゞ
是非ご活用ください!